一人一人のキャリアの可能性を広げる取り組み。OPEには実現できる環境が整っている
<インタビュー概要>
株式会社オープンアップITエンジニア(以下、OPE)では、社員一人一人のキャリアの可能性を広げるため、「就業とまなびの機会」を創り続け、企業理念の体現に努めています。
その最たるものとして、有志で集まった社員が、本業を行いながら任期制でCommunication Engineeringu推進部(以下、CE推進部)に兼務する「CEクルー制度」という活動に参加しています。
この制度を通じ、社員が社内活性化や個々の業務スキル改善に取り組んでいます。本記事では、CEクルーとして、さまざまな経験を重ねた勝田さんと立花さんに、CEクルー活動を実施する前後での変化や学びについて語っていただきました。
<プロフィール>
勝田 朋廣
株式会社オープンアップITエンジニア
事業統括本部 人事部 第一労務セクション兼第三労務セクション
Super Visor
兼CE推進部 メディアプロデュースセクション
クルー
立花 満理奈
株式会社オープンアップITエンジニア
採用本部 IT人材採用部 中途採用セクション
兼CE推進部 メディアプロデュースセクション
クルー
※登壇者のプロフィールは取材当時のものです。
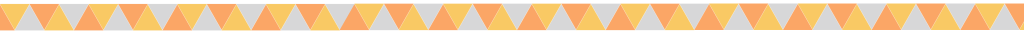

2024年10月より新たなCEクルーが加入!!
引き継がれる理念体現の取り組み。
OPEでは、組織活性化、人材育成という観点からCEクルー活動制度を設けています。この制度は9カ月間の任期制で、社内公募により選ばれたメンバーがCE推進部に集い、自身のキャリアの選択肢を広げられる様スキル改善や課題改善に取り組む制度です。「キャリアの可能性を秘めた全ての人に自信と展望があふれる世界を」という理念を基に、社員一人一人の選択肢を広げる活動が進んでいます。

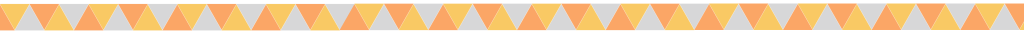
<インタビュー目次>
本業の業務内容

ー本業の業務内容を教えてください。
勝田:私は事業統括部人事部の人事第1労務セクションに所属し、主に労務管理全般を担当しています。たとえば、社員の産休や育休の手続き対応、関連する質問への回答などが主な業務です。また、人事労務第3セクションも兼務しており、こちらではエンジニアの労働時間管理などを行っています。
立花:私は採用本部IT人材採用部中途採用セクションで、未経験エンジニアの中途採用を担当しています。具体的には、面接官として求職者の採用面接を日々行っています。
ー本業でやりがいを感じる瞬間はありますか?
勝田:私の場合、育休や産休に関わる手続きを行っていると、社員のライフイベントに間接的に立ち会える瞬間があります。復帰面談でお子さんの声が聞こえたり、WEB会議などでカメラ越しにお子さんの姿を見られることもあり、そういった場面は心が和みますね。
立花:面接した方が入社後に活躍している話を聞くと、とてもやりがいを感じます。特に、自分が採用した方が社長賞やMVE(最優秀社員賞)を受賞したと聞いたときは、自分の仕事の成果を実感できて嬉しかったですね。
CEクルー活動前の課題点

ーCE推進部との兼任を行う前、課題に感じていることや改善したい点はありましたか?
立花:面接を通じて、候補者の魅力を十分に引き出せていないと感じることがあります。その原因として、私自身の主観が少し入りすぎてしまうことが課題だと考えていました。
勝田:私の場合、労務管理に必要な知識や経験がまだ十分ではないと感じています。特に産休や育休に関する業務では、女性特有の悩みに十分に寄り添えない部分が課題でした。
具体的な活動内容
ーお二人が参加されているCEクルー活動について教えてください。
立花:CEクルー活動は、任期は9カ月間で、社内公募で選ばれたメンバーが活動に参加します。私たちCEクルーが所属しているのはイベントプロモートセクションとメディアプロデュースセクションの2つがあり、私と勝田さんはメディアプロデュースセクションに所属をしております。
勝田:この活動では、OPEの企業理念でもある「一人一人のキャリアの扉を開きより豊かな人生への架け橋に」を元にCEクルーに新たな「就業とまなびの機会」の提供をしてくれる制度です。
そして主な業務内容として、組織の情報共有や活性化を担い、社内の牽引役となる人材を育成する制度でもあります。さまざまな部署から集まるメンバーで構成されるため、新しい視点や考え方を得る機会に恵まれており、自身にはなかった視点や新しい考え方など、「まなびの機会」が多々ある素晴らしい制度です。
ー具体的にはどの様な業務を行っているのでしょうか。
勝田:私のメインの担当は社内報コンテンツの制作ディレクションです。定期的に直接社員の手元に届く紙面と9月にリニューアルされたばかりの会社のアクティブなトピックを投稿し、情報共有を行う社内ポータルサイトの2つのディレクションをしています。
立花:私は基本的にはイベントプロモートセクションが運営しているイベントの広報リーダーを担当しており、メインで担当したのは社員総会です。社員総会も3か月に1度、WEBと対面で交互に実施されており、2つのセクションの間に立ち、広報ディレクションを行っておりました。

学んだことが本業でも活き、自信がついた
ー新たなサービスの立ち上げや会社の重要なイベントに深く関わっているのですね。業務を通して大変だったことはありますか?
立花:情報伝達が特に大変でした。社員総会のPMとしてディレクションを行う中で、メディアチームとイベントチームで連携を取る必要が多々あり、また、使用する動画に出演していただく他部門の方への調整など連携を上手に行わないとスムーズにいかず、小さなことでも情報共有していく必要性を改めて実感しました。
ーその中で成長できたことや学んだことはありますか?
立花:全体を俯瞰する能力が身に付いたと感じています。
CEクルー活動を始めた当初は自身が作業に没頭し、結果として全体を見ることができなくなり、負担が大きくなっておりました。
その反省を生かし、PMとして自身が作業の渦に巻き込まれてしまわないよう各メンバーに自走してもらうように進行いたしました。そうする事で全体を見る余裕が生まれ、課題が生じたときにフォロー可能な体制ができ、全体を俯瞰し、上手に運営する能力が向上しました。
勝田:私はコンテンツの制作ディレクションを通して、多くを学びました。元々は自身が伝えたいことのみを伝えられればよいと考えておりましたが、業務を通じてコンテンツ制作の先には必ず読み手がおり、誰に何を届けるか、という価値創造には苦労をしました。
また、任期の途中からコンテンツの専門家がメディアプロデュースセクションに配属されたことで、基本的な考え方から教えていただきました。そこから自分の中の意識が変わったと思います。
ーCEクルー活動を通じて、本業に活かせるなと感じる要素はありますか?
立花:CE活動を通じてOPEの考え方や理念など、目的をより深く理解できるようになりました。それが自分の中で腑に落ちたことで、本業での採用活動にもやりがいが増しています。
例えば、面接官として採用業務を実施している際でも、会話の中で多様な見方があることを求職者の方に伝えられるようになりました。
また、メールの文章一つとってもCEクルー活動の経験が活きています。
先ほど主観が入ってしまうことが課題だと申し上げましたが、CE推進部の方から指摘をいただき、自身の作成するメール、コンテンツに対する癖も改善できました。やはり、読み手目線で考えることが大切だと改めて教えていただき、些細なことでも物事を俯瞰してみてみると見方、捉え方が大きく変わることに気付きました。
勝田:CE活動で学んだ「逆算思考」や「ロジカルに説明するスキル」は、本業の労務管理における問い合わせ対応で非常に役立っています。以前よりも相手に寄り添った説明ができるようになり、成長を実感しています。先ほど申し上げた女性特有の悩みに寄り添ってあげることができないという課題に対しても相手に寄り添い、ロジカルに説明することができれば問題は解決することに気づきました。
CEクル-活動を始める前は物事の説明に自信がなかったのですが、しっかりと筋道を立てて説明することができるようになったと感じています。活動を通じて学んだ読み手のことを考えて作成した資料では、本業である人事部の上司からお褒めの言葉を頂き、成長を実感することができ自信を持てました。
これもCEクルーとして、自身で教わったことを吸収し、伝えることの基礎が身に付いたからこそだと思っています。個人的な課題として、アウトプット力がまだまだ弱いと感じており、今後の業務を通じて、改善していきたいと思っています。


キャリアの選択肢が広がる制度。理念を体現し続けるOPE
ー最後に、CEクルー活動を通じて感じた会社の魅力について教えてください。
立花:CEクルー活動は、他部署の人たちと協力しながら新しい視点を得られる貴重な機会です。任期制という限られた期間だからこそ、より集中して活動に取り組めます。このような制度を通じて、社員のキャリアの選択肢を広げる会社の姿勢に改めて魅力を感じました。
勝田:会社として「理念を体現する」という姿勢が非常に強いと感じており、CEクルー活動を含め、多様な経験を通じて自己成長ができ、今後のキャリアの展望が描きやすくなる環境が整っている点は、当社の大きな強みだと思います。
そして、最終的には自身でこの取り組みを社内に広めていきたいと思っております。
本業と並行してCEクルー活動に取り組むことで、新しいスキルや視点を得て成長を続ける勝田さんと立花さん。株式会社オープンアップITエンジニアは、社員一人ひとりの成長を支える環境づくりに注力しています。これからも、社員とともに企業としてさらなる発展を遂げていく姿に期待が寄せられます。






