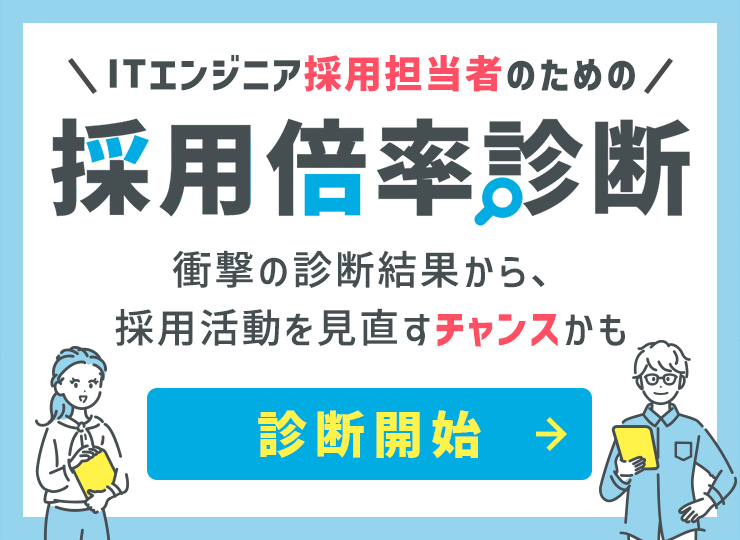エンジニアの仕事引継ぎを進める手順|要点や記載すべき内容も紹介
 エンジニア採用
エンジニア採用

仕事の引継ぎって何から始める?

エンジニアが転職する場合には、仕事の引継ぎが発生します。引継ぎが必要になった際に、何から始めれば良いのでしょうか?引継ぎを進める手順や、引継ぎ書に記載すべきこと、引継ぎのポイントをご説明します。
エンジニアの仕事引継ぎを進める手順5つ

業務を後任者に引き継ぐ場合、どのような手順で準備を進めていけば良いのでしょうか?エンジニアが業務を引き継ぐ手順を5つに分けて、それぞれの要点についてご説明します。
1:業務内容をリスト化する
まずは自分が担当している業務内容をリスト化することからはじめましょう。リスト化する際のポイントは、業務の大小に関わらず、思いつくものをすべて洗い出してリスト化することです。
理由は、抜け漏れがあると引継ぎ先がなく、誰もその業務を担当しない状態になってしまうためです。自分の判断でリスト化する・しないを決めるのではなく、思いつくすべての業務を漏れなくリスト化することがポイントです。
2:引継ぎの計画を立てる
業務の引継ぎを「いつまでに」「どのタイミングで」「どのように」するかを計画します。業務はワンタイムの業務と、継続的なルーティン業務に分けられます。ルーティン業務の場合は、その業務を実施するタイミングで一緒に引き継ぎ内容を説明すると、後任者からの質問に対してその場で説明できます。
ルーティン業務がない場合は、より一層丁寧に引継ぎをする必要があるため、引継ぎの計画をしっかり立てて、詳細の内容を後任者に説明する必要があります。
3:引継ぎ書の内容を考える
引継ぎ書の内容を実際に書き始める前に、まずはどのようことを引継ぎ書に記載するかの項目を考えます。例えば該当の引継ぎ業務に対する「作業フロー」「重要度や優先度」「関連メンバーの名前や連絡先」「関連データや利用ツールの保管場所」「保管場所へログインするためのID・パスワード」などです。
特に「関連メンバー」と「関連データの保管場所」は重要です。万が一、引継ぎ後に後任者に不明点が発生した場合でも、それらにアクセスすることで解決できる可能性が高まるためです。
4:引継ぎ書を作る
引継ぎ書の内容を記載していく際は、後任者の視点に立って記載することがポイントです。後任者はまだ引継ぎされる業務に関しての知識や経験が少ない可能性が高いため、できる限りわかりやすい内容で、体系的に記載する方が良いでしょう。
例えば、「図」「表」「箇条書き」などを適宜織り交ぜながら、読みやすい文書にした方が良いでしょう。読みやすさや後任者が加筆修正することを考えると、紙への手書きよりも、Wordなどのデータとして作成する方が後任者のためとなります。
5:後任の人に引き継ぐ
後任者に引継ぎ書に沿って説明します。単純に文書を渡すだけや読み合わせをするだけでなく、実際にその業務を一緒に進めながら説明することで、後任者の理解度をより深められます。
一方的な説明だけでなく、適宜、後任者からの質問を受け付けるタイミングを確保することで、後任者の不明点も減らせるでしょう。
引継ぎ書に記載すべき内容5つ

引継ぎ書を作成する場合、どのような内容を記載すれば良いのでしょうか?エンジニアが業務を引き継ぐ際に使用する引継ぎ書に関して、記載すべき内容を5つに分けてそれぞれの要点についてご説明します。
1:業務目的・要件について
まずは業務の目的や要件を記載することが重要となります。目的や要件を把握することで、何のためにこの業務は存在しているのか、どんな結果が期待されているのかを後任者が把握できるためです。
後任者が業務の目的や要件をしっかり把握できていれば、引継ぎ後に後任者がその目的に向けて業務を改善することも期待です。
誰のための業務なのか、この業務で自社にどのように役立つのかなどを具体的に記載することがポイントです。
2:社内システムの要件・導入目的について
社内システムの運用や保守を担当している場合、その要件や導入目的も記載します。後任者がそのシステムの要件や導入目的を理解できていないと、後任者が目先の対応や指示されたことだけを対応してしまう懸念があるため、なぜそのシステムが必要なのかの本質を伝えます。
そのシステムが存在している理由や背景、現状の課題、今後のロードマップなどを記載します。
詳細に関しては、システム設計書などの文書一覧を記載しておき、後任者が必要なタイミングで参照できるようにしておきます。
3:社内外の関係者一覧について
業務に関係する社内・社外の関係者を一覧化しておきます。理由は、後任者が引継ぎ後に業務で不明点があった場合などに、その社内外の関係者に連絡できれば解決できる可能性があるためです。
社内外の関係者に連絡する例は、「システムの仕様を確認したいとき」「システムで不具合が出たとき」などです。
関係者を一覧化しておくことで、後任者は何か問題があった際に質問できる先ができ、安心感にも繋がるでしょう。
4:業務の流れについて
業務の流れを具体的に記載します。自分にとっては当たり前の内容でも、後任者にとってはそうでない可能性がありますので、できるだけ暗黙知を残さないように詳細に記載することを心掛けます。
単に業務の流れや作業内容を記載するのでなく、その業務の背景、理由、他の業務とのつながりなどとあわせて記載すると良いでしょう。
作業内容を文章で記載するだけではなく、画面キャプチャなどとあわせて記載しておくことで、後任者の理解がより深まります。
別途マニュアルや手順書が存在している場合は、それらの格納先のURLやファイル名を記載します。
5:課題・トラブルなど現状について
課題が残っている場合は、課題の内容や重要度、優先度をつけて後任者に伝える必要があります。後任者がどの課題解決から着手して良いかがわかりやすくなっていることがポイントです。
トラブルが残っている場合も、内容やステータス、トラブルの関係者を後任者に伝えたほうがいいでしょう。関係者が怒っているケースや、慎重に対応が必要なケースなどは、詳細を引継ぎ書に記載しておくべきです。
エンジニアの仕事引継ぎの要点7個

エンジニアが引継ぎをする際、どのような内容を押さえておく必要があるのでしょうか?エンジニアが業務を引き継ぐ際の要点に関して、7つに分けてそれぞれをご説明します。
1:業務の手順をわかりやすく記載する
1つ1つの業務を説明するだけでなく、業務の全体像を説明したうえで、前行程や後工程の業務など、業務全体の流れを伝えた方が良いでしょう。
業務の全体像がわかると、後任者の業務理解も深まりますし、将来的に業務フローが変更になった際も、後任者がスムーズに対応できるでしょう。
2:人間関係なども共有する
業務に関連する関係者を共有することも重要です。理由は、後任者が困った際に自分で解決できないことを、関係者に確認できるためです。
例えば、「不明点があるが誰に聞けば良いのかわからない」「必要なデータを誰が持っているのかわからない」などの問題が発生するリスクを下げられます。
3:後任・関係者と必ずコミュニケーションをとっておく
後任に引き継ぐ際に、関係者と後任者の顔合わせの場をセットし、事前にコミュニケーションをとってもらうと良いでしょう。それができていると、後任者が関係者の顔と名前を確認でき、より円滑なコミュニケーションをとれるでしょう。
事前に顔合わせができない場合は、メールなどで後任者と関係者をそれぞれ紹介しておくだけでも良いでしょう。
4:担当業務を洗い出し記載する
担当業務を洗い出して漏れなく引継ぎ書に記載しておくことも重要です。担当業務の引継ぎが漏れていると、後任者がその業務を実施せずに放置され、問題になってから発覚するリスクがあるためです。
例えば引き継ぐ数週間前から自身の業務を進めながら業務の洗い出しを進め、漏れなく引継ぎ書に記載しておくと良いでしょう。
5:引継ぎ書・マニュアルはデータでも残す
引継ぎ書やマニュアルはデータでも残すことがポイントです。データで残している場合はテキスト検索できますし、将来的に業務内容が更新された場合でも、後任者がデータを更新できます。
後任者がその後任者に引き継ぐ際も、データで引継ぎ書が残っていれば、それを更新するだけで引継ぎ書が完成します。
6:文章だけで引継ぎをしない
文章だけで引継ぎせず、図や表を含んだ引継ぎ書にすると良いでしょう。なぜなら、図や表を活用して見やすくわかりやすい引継ぎ書にすることで、後任者の理解が深まるためです。
比較表や画面キャプチャ、場合によっては動画などを活用し、できるだけ文章だけで引継ぎしないことがポイントです。
7:後任者の立場に立って引き継ぐ
一方的に引継ぎ書だけを渡して、「わからなかったら聞いて」だけを伝えるなど、自分本位な引継ぎにならないように注意が必要です。
後任者の理解を深めるためには、一方的に伝えるだけではなく、双方向のコミュニケーションが必要です。
例えば、対面で説明する場をセットし、適宜質問を受け付ける時間を設けるなど、後任者の立場に立った引継ぎが必要です。
仕事引継ぎ後にすべき事とは

引継ぎ書の作成とその説明が終わったとしても、それで業務から完全に手を引くのではなく、後任者が業務を開始した後に適宜声をかけることもポイントです。
理由は、引継ぎ書を渡したとしも、実際の業務を進めてみると疑問が発生しますし、引継ぎ漏れが残っている可能性もあるためです。
例えば、「問題なく業務ができているか」「新しい質問がないか」など、適宜コミュニケーションを取ることをおすすめします。
また、社内外の関係者に、業務から離れることを連絡しておきましょう。転職後もそれらの関係者と何らかの関わっている可能性もありますので、信頼関係を失わないことが重要です。後任者へ引継ぎをしたことや、今までの感謝を伝えることがポイントです。
要点をしっかり押さえて仕事引継ぎを済ませよう!

業務の引継ぎを始める際は、まずどんなに小さなタスクからでも構わないので、自分のやっている仕事の洗い出しから始めましょう。その後要点をおさえながら、引継ぎ資料の作成を進めてみてください。
要点さえ押さえておけば、詳細は後からでも関係者に確認することもできるためです。例えば、全体像や業務フロー、ポイントとなる業務とそのデータの格納先など、まずは要点をしっかり押さえて引継ぎすることが重要です。
この記事の監修者・著者

- AWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
-
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが4,715名在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1,154名(2024年6月現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者276名在籍(2024年5月現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2024年6月時点)
最新の投稿
- 2024-12-27営業インタビュー情報共有の活性化の中心に。SP企画部の新たな取り組み
- 2024-07-01営業インタビュー最短で当日にご提案可能。 OPE営業の対応が早い3つの理由
- 2024-07-01営業インタビュー研修見学ツアーが高評価!「お客様のOPEに対する期待を高め、継続に貢献できればと思います。」
- 2024-07-01営業インタビュー信頼関係を構築し、エンジニアの長期就業へ

- 求人・転職サイトや自社採用サイトを使っているが、自社に合ったITエンジニアが応募してこない…
- すぐに採用したいが、応募がぜんぜん集まらない
オープンアップITエンジニアをご検討ください!
当社のITエンジニア派遣サービスは
- 派遣スピードが速い!(最短即日)
- 4,500名のエンジニアから貴社にマッチした人材を派遣
- 正社員雇用も可能
こんな特長があり、貴社の事業やプロジェクトに合った最適なITエンジニアを派遣可能です。
まずは下記ボタンから無料でご相談ください。