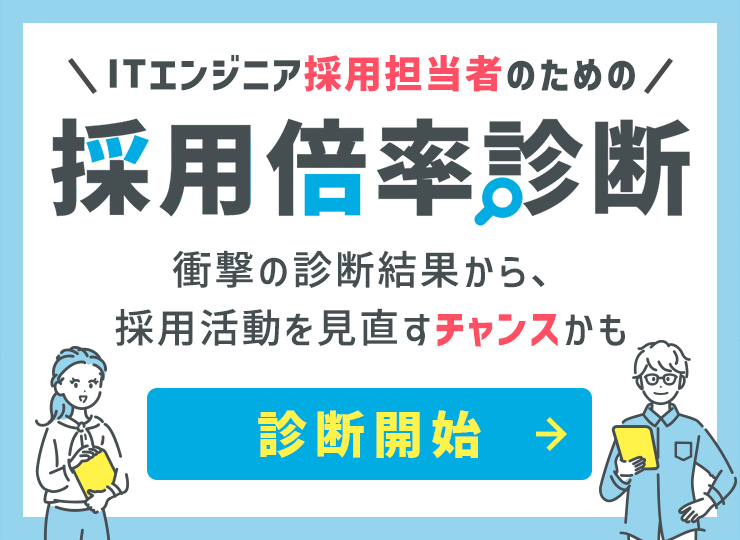リフレッシュ休暇とは?メリット6つと導入するときのポイントを解説
 エンジニア採用
エンジニア採用

リフレッシュ休暇とは?
リフレッシュ休暇は、労働者の疲労回復を目的として付与される休暇です。業務を継続してきたことをねぎらう意味合いもあり、「リフレッシュ」を目的としています。
リフレッシュ休暇は企業が独自に定めているため、企業ごとに内容が異なります。これからリフレッシュ休暇の概要について紹介します。
リフレッシュ休暇の条件
リフレッシュ休暇は、勤続年数により設定している企業が多くなっています。例えば、入社5年目、10年目、20年目といった節目の年に、リフレッシュ休暇を取得する方法です。
その他には、年齢によって取得できる企業や、休暇中に短期留学などの特別な体験をすることを条件としている企業もあります。
リフレッシュ休暇の日数
リフレッシュ休暇の日数は、企業により異なります。勤続年数が条件の場合には、年数の長さに応じて休暇日数も長くなるのが一般的です。例えば、5年目では5日、10年目と20年目は10日といった具合です。
5日の休暇では週末を含めて9連休以上、10日の場合は2週間の休暇をとれます。さらに年末年始休暇や5月連休と連結し、長期休暇とする場合もあります。まとまった期間の休暇を利用し、旅行などでリフレッシュできます。
有給休暇との違い
有給休暇は、法律で最低条件が規定されており、どの企業でも従業員への付与が義務付けられています。
有給休暇の取得については、入社後6か月経過していることの他に、その期間の全労働日の8割以上出勤していることという要件があります。要件を満たすと10日以上の有給休暇が付与され、従業員はこれを取得する権利を持っています。
リフレッシュ休暇は、企業が独自に決める「特別休暇」の1つです。その内容や条件は、企業が独自に定め、運用しています。
企業の義務ではない
年次有給休暇や育児休暇などは、法律で定められた「法定休暇」です。これに対してリフレッシュ休暇は「法定外休暇」となっています。企業にはリフレッシュ休暇制度を導入する義務はありません。
リフレッシュの導入にあたっては、企業内で労使の話し合いにより、取得条件や取得日数などを任意に設定できます。
リフレッシュ休暇制度の導入状況
リフレッシュ休暇制度を導入している企業は、増加している傾向があります。厚生労働省の調査によると、平成31年にリフレッシュ休暇制度を導入している企業の割合は、社員1,000人以上の企業の場合、46.5%でした。大企業ほど導入が進んでいます。
リフレッシュ休暇の平均付与日数は5.5日となっており、賃金を全額支給する企業の割合は95.9%となっています。
リフレッシュ休暇のメリット6つ
リフレッシュ休暇は、企業側にとっても従業員側にとってもメリットがあります。従業員のメリットは休みが増えるということです。長めの休暇により、心身の回復を図ったり、旅行など普段できない活動ができたりします。
企業側にとっては、従業員の労働意欲を向上させる効果があります。また、求人募集でアピールできるなど、企業イメージを上げるメリットがあります。
これから、リフレッシュ休暇のメリット6つについて紹介します。
リフレッシュ休暇のメリット1:モチベーションの維持・向上
毎日働き続けることは、心身の疲労の蓄積やマンネリ化につながります。休暇で何日か仕事から離れることで、仕事のストレスから解放され、身体的にも精神的にもリフレッシュできます。
計画的に取得するリフレッシュ休暇は、休暇を目的に頑張ろうという気持ちを起こさせ、モチベーションの維持に役立ちます。また、リフレッシュ休暇取得により再び仕事へのモチベーションが上がり、新たな気持ちで再び仕事に取り組むことができます。
リフレッシュ休暇のメリット2:従業員の業務の幅が広がる
リフレッシュ休暇で長期間不在になる人の代わりに、他の人が休暇中の業務を担当する場合があります。代わりに業務を担当する人にとっては、普段と違う業務内容や役割を経験することになります。
メンバーが計画的に不在になる機会を、職場全体で従業員の仕事の幅を広げるチャンスとして利用すれば、企業にとってもメリットになります。
リフレッシュ休暇のメリット3:生産性の向上
リフレッシュ休暇は、心身がリフレッシュして生産性が向上する効果の他に、休暇の前後で業務を見直すことによっても生産性向上につながります。
長期休暇に向けて業務を計画的に前倒ししたり、休暇後のスケジュールを調整したり、休暇中の仕事を別の人に割り当てたりと、業務スケジュールを見直す機会になります。これらは、従業員にとっても職場としても、生産性の向上につながります。
リフレッシュ休暇のメリット4:新しいアイデアが生まれる可能性がある
リフレッシュ休暇は長期で計画的に取得することが多いので、社員は旅行やレジャーなど、普段の生活から離れた活動を行います。非日常の体験は、脳をリフレッシュさせ、新たなアイデアの創造力を活性化します。
毎日会社に通う単調な生活をしていた脳にとっては、環境が変わるだけでも大きな刺激で、新たな思考回路が生まれやすくなります。仕事に戻ったときにも、新しいアイデアを活かした発想で業務を行うことが期待できます。
リフレッシュ休暇のメリット5:離職を防ぐことができる
リフレッシュ休暇を導入すると従業員の会社への愛着心は高まり、離職を減らすことにつながります。また、リフレッシュ休暇は5年毎などに取得できるため、次のリフレッシュ休暇まで働こうという目標になり、離職を遅らせる要因になります。
離職したいと思ったタイミングの翌年がリフレッシュ休暇だと、「来年のリフレッシュ休暇後に辞めよう」と思い、リフレッシュ休暇取得後には、また仕事を続けようと思うこともあります。
リフレッシュ休暇のメリット6:求人募集でアピールできる
求人に応募する人は、求人情報で休暇については必ずチェックするでしょう。通常の週休の日数や曜日は大事なポイントですが、その他に特別休暇の記載があることは魅力です。
リフレッシュ休暇があることは、休暇が充実している企業である印象を与え、求人情報のアピールポイントになります。
リフレッシュ休暇導入のポイント6つ
リフレッシュ休暇制度を取り入れるには、規則制定や職場の環境づくりなどが必要です。就業規則の見直し、取得条件の明確化の他に、休暇をとりやすいように職場の意識を変えたり、業務のルールを見直したりすることも重要になります。
ここでは、スムーズにリフレッシュ休暇を導入するためのポイントを6つ紹介します。
リフレッシュ休暇導入のポイント1:休みやすい環境づくりをする
リフレッシュ休暇を導入しても活用できない1番の原因は、休暇をとりにくい職場の雰囲気の場合があります。休暇という権利を行使せず、周囲に迷惑をかけるからと遠慮しがちな方も多いことでしょう。
職場内で各メンバーが順番に休みやすい雰囲気を作り、仕事を協力し合える体制を作るために、管理職は意識改革と業務効率化の方策を考えていくべきです。
リフレッシュ休暇導入のポイント2:取得可能な日程や条件を明確にする
リフレッシュ休暇は毎年取るものではないので、対象の従業員本人も、職場の上司や同僚も、その取得条件を忘れてしまいがちです。取得可能な日程、勤続年数などの条件を明確にし、規則などでいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
対象者と職場がリフレッシュ休暇について正しく認識することで、計画的に取得できるようになります。対象年度の従業員と上司に、個別にメールなどで周知することも効果があります。
リフレッシュ休暇導入のポイント3:業務におけるルールを見直す
リフレッシュ休暇では、対象者が長期間不在になります。長期出張のようにメールで連絡をとることもできません。リフレッシュ休暇をスムーズに運用するためには、休暇中も業務が滞らないように、休暇前にスムーズな引継ぎができる必要があります。
そのために、日頃から業務のルールを見直し、複数の人が担当できるようにしておくことや、状況を共有しておくことが大事です。
リフレッシュ休暇導入のポイント4:柔軟な対応・運用をする
リフレッシュ休暇を予定していても、事業計画の変更などで、休みを取れない状況になることがあります。
取得対象の年度に他社に出向し、出向先にリフレッシュ休暇制度がないために取得権利を逃した例もあります。その他、世界情勢により目的の海外留学が中止になることもあります。
状況が変わった場合には、単に休暇を中止するのではなく、時期を延期するなど、従業員のモチベーションを下げないような柔軟な運用が大事です。
リフレッシュ休暇導入のポイント5:就業規則を見直す
リフレッシュ休暇の内容は企業によって異なりますので、就業規則で内容を取り決めておくことが大事です。定めておく内容には、対象となる勤続年数、取得日数、給与の扱いなどがあります。
就業規則に盛り込んだ内容は、社内報や労働組合を通じて従業員に周知することも重要です。
リフレッシュ休暇導入のポイント6:取得する意識を高める
休みをとると周囲に迷惑がかかるという風土が残っている職場では、リフレッシュ休暇を取りづらくなります。休暇の取得は従業員の権利です。従業員が積極的にリフレッシュ休暇を取得するように、社内の意識を高める必要があります。
上司がリフレッシュ休暇の取得を促す声かけを行うことで、職場の意識が変わります。また、上司自らが、率先して休暇をとることも重要です。
リフレッシュ休暇中の給料は?
リフレッシュ休暇の制度内容は、企業が独自に決めるため、給料についても有給か無給かを事前に定めておく必要があります。
厚生労働省の平成31年の調査では、賃金を全額支給する企業の割合は95.9%となっています。労働をねぎらい、リフレッシュしてもらう趣旨の休暇なので、有給であることがほとんどのようです。
リフレッシュ休暇の導入を検討しよう
リフレッシュ休暇は、企業が独自に定める特別休暇です。主に勤続年数を条件とした休暇で、長年の労働をねぎらい、従業員に心身共にリフレッシュしてもらうことを目的としています。
リフレッシュ休暇は従業員にとってメリットがあるだけでなく、企業イメージの向上や求人でのアピール、離職の防止など、企業にとってもメリットがあります。リフレッシュ休暇導入のポイントを参考にして、制度の導入を検討してみてください。
この記事の監修者・著者

- AWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
-
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが4,715名在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1,154名(2024年6月現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者276名在籍(2024年5月現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2024年6月時点)
最新の投稿
- 2024-12-27営業インタビュー情報共有の活性化の中心に。SP企画部の新たな取り組み
- 2024-07-01営業インタビュー最短で当日にご提案可能。 OPE営業の対応が早い3つの理由
- 2024-07-01営業インタビュー研修見学ツアーが高評価!「お客様のOPEに対する期待を高め、継続に貢献できればと思います。」
- 2024-07-01営業インタビュー信頼関係を構築し、エンジニアの長期就業へ

- 求人・転職サイトや自社採用サイトを使っているが、自社に合ったITエンジニアが応募してこない…
- すぐに採用したいが、応募がぜんぜん集まらない
オープンアップITエンジニアをご検討ください!
当社のITエンジニア派遣サービスは
- 派遣スピードが速い!(最短即日)
- 4,500名のエンジニアから貴社にマッチした人材を派遣
- 正社員雇用も可能
こんな特長があり、貴社の事業やプロジェクトに合った最適なITエンジニアを派遣可能です。
まずは下記ボタンから無料でご相談ください。