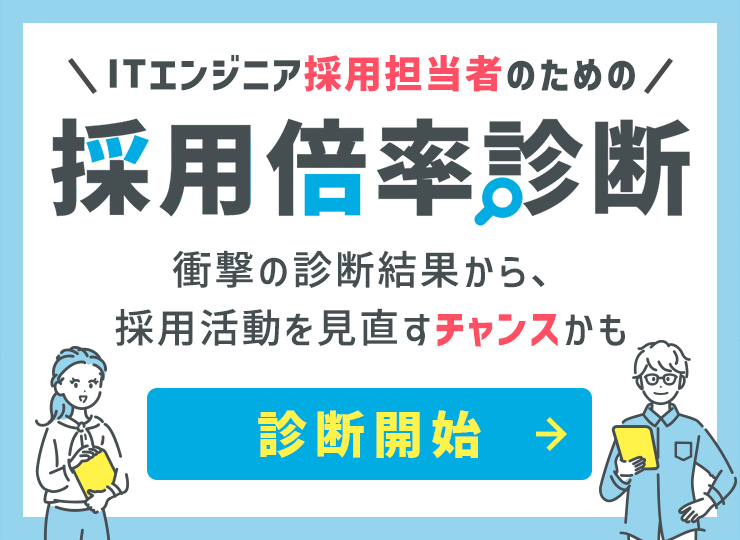有給休暇とはどんな制度?消化率を上げる方法4つやマナーについても紹介
 エンジニア採用
エンジニア採用

有給休暇とはどんな制度?
有給休暇とは、賃金が発生する休暇日のことです。
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」といい、労働基準法第39条により定められています。使用者からあらかじめ指定された休日である「公休日」とは別に取得できるものであり、労働者の権利とされています。
有給休暇は、労働者の心身を回復してゆとりのある生活を保障するものです。これにより、労働意欲や生産性の向上が期待されています。
有給休暇の対象者はどんな人?
有給休暇の対象者は、「雇い入れの日から6カ月経過」、「全労働日の8割以上出勤」という2つの条件を満たす労働者です。
「全労働日」とは、算定期間(雇い入れ日から6カ月間、以後1年ごと)から公休日を除いた日数をいいます。
有給休暇の対象者は正社員だけではありません。6カ月経過し、全労働日の8割以上出勤している場合は、パートやアルバイトにも有給休暇が発生します。
有給休暇の日数
勤続期間が長くなるにつれて、有給休暇の付与日数は増えていきます。
全労働日の8割以上出勤している場合、入社から6カ月が経過した時点で、有給休暇が10日付与されます。勤続期間1年6カ月で11日、2年6カ月で12日付与され、それ以降は1年ごとに有給休暇が2日ずつ増えていきます。
6年6カ月で付与日数20日となり、以後の付与日数は毎年20日間です。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6カ月 | 10日 |
| 1年6カ月 | 11日 |
| 2年6カ月 | 12日 |
| 3年6カ月 | 14日 |
| 4年6カ月 | 16日 |
| 5年6カ月 | 18日 |
| 6年6カ月以上 | 20日 |
有給休暇を取れる日数
有給休暇を取れる日数について、明確な定めはありません。
有給休暇は、原則として1日単位で取得するものであり、使用者は半日単位で付与する義務はないとされています。
しかし、半日単位での付与が出来ない訳ではありません。労働者の申し出を使用者が認めた場合は半日の付与が可能であり、会社の判断や裁量に委ねられています。
有給休暇を付与されたらいつまでに使わないといけないの?
有給休暇には時効があり、付与されてから2年経過すると消滅します。
2018年4月1日入社の場合、6カ月後の同年10月1日に10日間(A)、さらに1年後の2019年10月1日に11日間(B)の有給休暇が付与されます。(A)の消滅時効は2020年10月1日です。
有給休暇は古いものから消化されます。2020年9月末までに有給休暇を8日間取得した場合、Aのうち未消化の2日分は、2020年10月1日に消滅します。
有給休暇が義務化された理由
2019年4月1日より、働き方改革・休み方改革の一環で有給休暇の取得が義務付けられました。義務化の理由は、有給休暇の取得率の低さを解消するためです。
有給休暇の義務化は、「働きすぎ」の防止、労働環境の改善を目的としています。
義務化されたことで変更になったルール
前述のとおり、有給休暇取得義務の対象者は、10日以上の有給休暇が付与される労働者です。変更されたルールでは、労働者に「年5日」の有給休暇を取得させることが使用者に義務付けられました。
使用者には、労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」を作成する義務があります。また、有給休暇取得の義務化により、基準日(有給休暇付与日)、日数(取得日数)、時季(取得した日付)の3項目が追加されました。
有給休暇を消化する際のマナー3つ
ここまで見て来たように、有給休暇は労働者の権利です。しかしながら、権利を主張して好き勝手に消化して良い性質のものではありません。社会人として、また会社の一従業員として、有給休暇を消化する際にはマナーを守ることが大切です。
ここでは、有給休暇を消化する際のマナーについて、ポイントを3つご紹介します。有給休暇を申請する際には、相手が快く承諾してくれるように、マナーを守りましょう。
有給休暇を消化する際のマナー1:ある程度日程の余裕を持って申請する
有給休暇は、事前申請が原則とされています。労働基準法上では、申請時期について特段の定めはありませんが、余裕を持って申請するのが理想的です。
会社で「○日前までに申請」というルールがある場合は、期間内に申請するようにしましょう。
ただし、体調不良や事故など、一定期間前に申請することが難しいケースがあります。多くの会社では、このような場合は事後申請が認められています。
有給休暇を消化する際のマナー2:退職する前であれば2か月前ほど余裕を持つ
退職時に有給休暇を消化する場合、2カ月前には申請すると良いでしょう。
民法上では2週間前の申告での退職が認められていますが、1~2カ月前の申し出が一般的とされています。退職日までに有給休暇を消化することを考慮すると、2カ月程度の余裕を持って知らせておくことが理想です。
退職前に、有給休暇の保有日数と公休日を確認しておきましょう。
有給休暇を消化する際のマナー3:退職する場合は引継ぎをしっかりと行なう
労働者が退職する場合、その業務は後任者へと引き継がれます。円満退職のためにも、退職日までにしっかりと引継ぎを行うことが重要です。
退職が決定したら、有給休暇の消化、引継ぎ期間を考慮した上でスケジュールを組む必要があります。
「引継ぎに時間が掛かり、残っている有給休暇を消化できない」、「引継ぎが満足に出来なかった」という事態を避けるため、余裕を持って退職の意思を会社に伝えるようにしましょう。
有給休暇の消化率を上げる方法4つ
ここからは、有給休暇の消化率を上げるための方法について見て行きましょう。
統計によると、2019年の有給消化率は52.4%で、前年より1.3%上昇したと言う結果が出ており、中には休暇制度の見直し・改善を行うことで消化率が大幅にアップした企業もあります。
では、どのような方法で有給休暇の消化率を上げていったのでしょうか。以下に、参考となる4つの方法をご紹介して行きます。
有給休暇の消化率を上げる方法1:時間単位の取得制度を導入
1つ目は、「時間単位の有給休暇取得制度」の導入です。
有給休暇は1日単位での取得が原則ですが、労使協定を締結することで、年5日を上限として時間単位での取得が可能です。
有給休暇の取得率の低さには、「周囲に負担が掛かるので取りづらい」と思ってしまう背景があります。その点を配慮し、時間単位の取得制度では、通院や短時間の用事の際に柔軟に有給休暇を取得できる可能性があります。
有給休暇の消化率を上げる方法2:有給化が取りやすい環境作り
2つ目は、労働者が有給休暇を取りやすい環境作りです。
個々に仕事を抱えているため、休みづらいという企業は多いでしょう。労働者一人一人の業務内容や量、手順を会社内で共有し、いつでも他の人がサポートできる体制を整えることがポイントです。
独自の休暇制度を取り入れている会社もあります。誕生日や結婚記念日などのアニーバーサリー休暇のほか、連休取得を義務付けるものや失恋休暇など、ユニークな休暇があります。
有給休暇の消化率を上げる方法3:交代制などの人数調整
3つ目は、人数調整をすることで消化率を上げる方法です。
いくら有給休暇が労働者の権利といっても、自分だけ休むのは気がひけるという人も多いのはないでしょうか。しかし、業種によっては全員が一斉に休むと業務に支障が出てしまう可能性もあります。
その場合は、交代制で休暇を取得できるように調整することで、有給休暇を取得する上での抵抗感や不公平感を無くすことができるでしょう。
有給休暇の消化率を上げる方法4:計画的付与制度を活用する
4つ目は、「計画的付与制度」の導入です。
計画的付与制度とは、労使協定を締結した上で、有給休暇付与日数のうち5日を除いた日数について休暇取得日を計画的に割り振ることが可能な制度です。
この制度では、使用者があらかじめ休暇日を決めるため、有給休暇の消化率が上がります。
使用者は労務管理や業務計画が円滑になり、労働者の方も、会社から指定された休暇のため心理的な負担がなく有給休暇を取ることができます。
一斉付与方式
「一斉付与方式」とは、事業所全体を休みにすることで、全労働者に同一の日に有給休暇を取得させる方式です。
企業または事業所全体で計画年休を設定します。
この方法は、製造業のように稼動を止めて全労働者を休ませることが可能な企業に導入されています。一斉に稼動を止めることにより、経費削減できるというメリットもあります。
交替制付与方式
「交代制付与形式」とは、班やグループ別に交代で有給休暇を付与する方式です。
流通業やサービス業などのように、労働者を一斉に休ませたり定休日を増やすことが難しい企業で活用されています。
業務への影響を最小限に抑えつつ、有給休暇の消化率を上げられる合理的な方法です。
個人別付与方式
「個人別付与方式」とは、有給休暇を付与する日を、個人別に設定できる方式です。
ゴールデンウィーク、夏季、年末年始に加え、誕生日や結婚記念日など、労働者個人の都合に合わせて休暇を取得することができます。ただし、自由な反面、有給休暇の管理が難しいというデメリットがあります。
この方式の場合は、労働者が希望日を記載した「年次有給休暇付与計画表」をもとに、使用者が個別に付与日を決定する方法が一般的です。
有給休暇の日程変更を依頼する「時季変更権」について知ろう
使用者には、原則として労働者が希望する日に有給休暇を付与する義務があります。しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」は、取得日の変更を促す「時季変更権」を行使できます。
ただし、有給休暇を付与すること自体を拒否することはできません。
労働者が一斉に有給休暇の申請をして適正な人員を確保できない場合、その日にその労働者にしかできない業務がある場合などは、時季変更権が認められます。
有給休暇について学んでしっかりと有給取得できる環境にしよう
労働者の健康と安全を守るためにも、企業全体が有給休暇の取得について注力する必要があります。
この記事では、有給休暇制度の概要、有給休暇の消化率を上げるための方法などをご紹介しました。有給休暇への理解を深め、労働者にとってより良い環境作りを目指しましょう。
この記事の監修者・著者

- AWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
-
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが4,715名在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1,154名(2024年6月現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者276名在籍(2024年5月現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2024年6月時点)
最新の投稿
- 2024-12-27営業インタビュー情報共有の活性化の中心に。SP企画部の新たな取り組み
- 2024-07-01営業インタビュー最短で当日にご提案可能。 OPE営業の対応が早い3つの理由
- 2024-07-01営業インタビュー研修見学ツアーが高評価!「お客様のOPEに対する期待を高め、継続に貢献できればと思います。」
- 2024-07-01営業インタビュー信頼関係を構築し、エンジニアの長期就業へ

- 求人・転職サイトや自社採用サイトを使っているが、自社に合ったITエンジニアが応募してこない…
- すぐに採用したいが、応募がぜんぜん集まらない
オープンアップITエンジニアをご検討ください!
当社のITエンジニア派遣サービスは
- 派遣スピードが速い!(最短即日)
- 4,500名のエンジニアから貴社にマッチした人材を派遣
- 正社員雇用も可能
こんな特長があり、貴社の事業やプロジェクトに合った最適なITエンジニアを派遣可能です。
まずは下記ボタンから無料でご相談ください。